土壌汚染と不動産価格評価について−その3

「その道の人に聞く」は、「土壌汚染と不動産価格評価について」と題し、日本不動産研究所の平倫明様にお話しをお聞きしています。
前回は、「土壌汚染と不動産鑑定評価(その1)」として、「不動産鑑定評価とは?」「土壌汚染がある場合どのように鑑定評価を行うのか?」についてお話しいただきました。
今回は、「土壌汚染と不動産鑑定評価(その2)」として、「これまでの不動産市場における土壌汚染の対応と評価の実態」についてお話しをいただいています。
環境プロジェクト室の設置が平成15年とのことでしたが、平成15年といえば、土壌汚染対策法が施行された年ですね。土壌汚染対策法の施行によって、不動産鑑定評価に関して基準の変更はあったのですか?
平成14年7月の不動産鑑定評価基準改正(平成15年1月1日施行)で、「土壌汚染」は不動産の価格を形成する要因である旨が明記されました。
この時の基準改正は、先ほど(前回記事)お話ししました、バブル経済の崩壊後、不動産市場の価値判断が収益性へとシフトし、その収益力を的確に反映させる鑑定評価に対する新しいニーズに対応することを主眼とした大きな改正だったのですが、その一つとして、土地に関する「土壌汚染」のほか、建物の「アスベスト」や「PCB」の使用といった、有害物質の存在が不動産の価値に大きな影響を及ぼしていることから、これらの要因が価格を形成する要因である旨が明確化されたわけです。
「土壌汚染」については、もちろん「土壌汚染対策法」が施行されることもその背景にあって、「不動産鑑定評価基準」「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」(以上、国土交通省)の改正が施行されるのに先立ち、(社)日本不動産鑑定協会(国と業界を繋ぐ組織、DOWAさんの業種で言えば(社)土壌環境センターさんと同様な組織と考えて頂ければと思います。)が、実務の具体の対応指針として「土壌汚染に関わる不動産鑑定評価上の運用指針Ⅰ」を平成14年12月に作成しています。その後に作成された「同 運用指針Ⅱ」を含め、土壌汚染の対応については「基準」「留意事項」「運用指針Ⅰ及びⅡ」が、実務上遵守すべき規定ということになります。
環境省が調査している土壌調査事例・汚染判明事例の推移では、平成15年以前の平成10年頃から事例数がぐっと増えています(図1)。不動産鑑定評価基準の改正や実務上の規定が定められたのは、そんな流れの中でニーズが高まったということなんでしょうか?
この調査は、各自治体が把握している事例を集計したものですので、不動産取引の実態そのものとは言えませんが、その数の変化は不動産市場の動きを現しているものと認識しています。
このグラフ(図1)に赤丸をしてみましたが、これはそれぞれ調査事例・汚染判明事例数が大きく増加したところを示しています。この要因として、グラフにも記載されているように土壌環境基準の設定からその項目が追加されていく過程で土壌汚染への関心が高まり、さらに土壌汚染対策法の施行がトリガーとなった、といったような説明が一般的かと思います。そのとおりだと思いますが、実はこの赤丸をした3つの時期は不動産市場の特徴的な動きと符合しています。
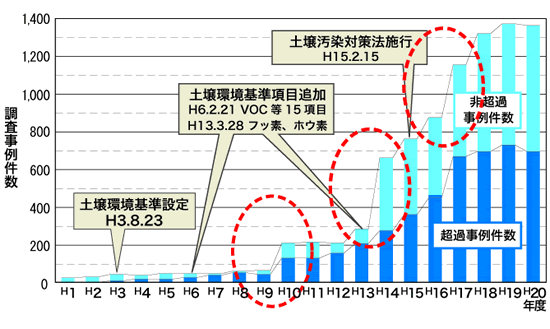
図1 年度別の土壌汚染調査事例
出典:環境省(水・大気環境局)「平成20年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例に関する調査結果」(H22年3月)
1番最初の赤丸(平成10年頃)については、ちょうど外資系のファンドが日本に参入してきた時期にあたります。
そして、2番目の赤丸(平成14年頃)は、まさにJ-REIT創設の時期であり、不動産取引において顕在化した土壌汚染問題が新聞紙上などで騒がれた時期です。もちろん、土壌汚染対策法制定の動きがあった時期でもあります。
3番目の赤丸(平成17年頃)は、顕著な増加傾向を示している中で、さらに事例数が増加した時期ですが、これはJ-REIT銘柄数が顕著に増加し、時価総額及び東証REIT指数が一気に上昇した時期と合致しています。
こうした動きとの連動を考えますと、このグラフ(図1)からも土壌汚染対策法制定以前から不動産市場では土壌汚染リスクが顕在化していたということが言えますし、こうした法の制定・施行といった過程を経て、不動産市場において土壌汚染リスクの認識が広がっていったという見方ができると思います。
では、同じ環境省調査による汚染判明事例の対策内容(図2)については、どのようにお考えになりますか?
これは先ほどの汚染判明事例(図1)の対策実施内容を集計した累計値で、時系列の推移を現したものではありませんが、これまでの不動産市場で多く選択されてきた対策方法と符合していると思います。
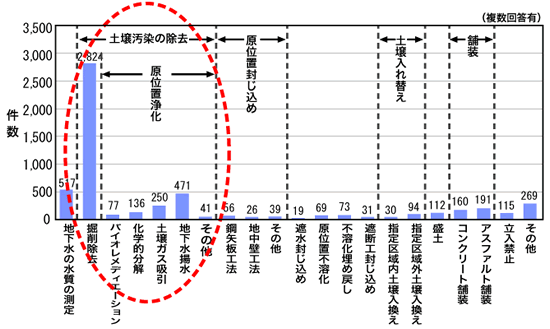
図2 措置の実施内容(超過事例(累計))
出典:環境省(水・大気環境局)「平成20年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例に関する調査結果」(H22年3月)
このグラフ(図2)から、赤丸部分が全体の大半を占めていることがわかります。その方法は、土壌汚染対策法の区域指定が解除される方法である「土壌汚染の除去」、すなわち「浄化」することであり、その中でも際立っているのが「掘削除去」となっています。
土壌汚染対策法では汚染が判明しても決して「土壌汚染の除去(=浄化)」を義務づけてはいません。グラフ(図2)の横軸にも記載されているように、人への健康被害を防止する対策として「立入禁止」「覆土」「封じ込め」などの様々なメニューが定められていますが、これまでの不動産市場における取引では、自主的な対策として「掘削除去」が前提とされてきた、ということがこのグラフからも言えるかと思います。
これを簡単な絵にすると、このような関係になるかと思います(図3)。
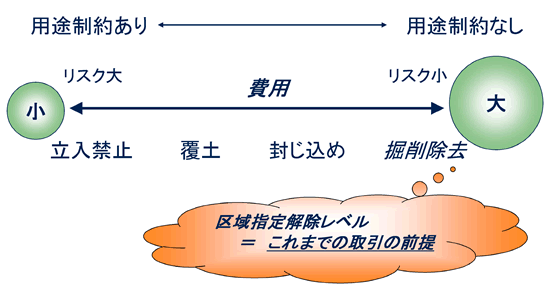
図3 対策レベルとリスク・用途の多様性
土地利用(=用途の多様性)の観点からすると、土壌汚染を残置する対策は、その対策に際して高額な費用はかからないが、土壌汚染が存在している状況であり、例えばここに住宅を開発することについてはエンドユーザーに忌避される可能性がありリスクが大きい、したがって開発する用途の制約が出てくる。こうしたリスクを最小化するため、対策費用は増大するが、土壌汚染を「浄化」することで、土壌汚染がない場合と同様の用途の多様性がある土地として取引する。
これが、これまでの不動産市場が選択したきた判断認識だと考えています。
そうすると、先ほど(前回記事)お話し頂いた土壌汚染が不動産の価値に影響を与える2つの要素(対策費用とスティグマ)は、これまでの不動産市場からすると、どのような関係になるのですか?
対策方法に応じた費用・スティグマの関係を示したのが、この図(図4)になります。
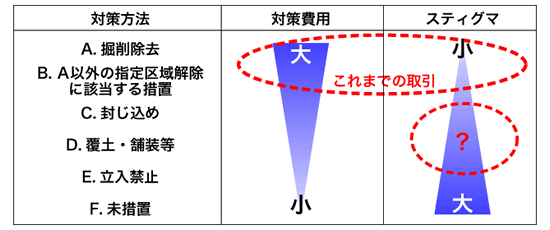
図4 対策方法及び費用とスティグマの関係
そして、赤丸(図4)で示したのが「これまでの取引」の2つの要素の関係ということになりますが、対策費用については、「掘削除去」にかかる費用がその前提となります。一方、スティグマについては、「掘削除去」という対策方法が、敷地全域の土壌汚染の有無及びその状態を土壌調査等により確定のうえ、汚染された範囲の全量をきれいな土壌に入れ替える対策ですから、こうした対策を前提としたこれまでの取引にあたっては、スティグマによる減価が顕在化していないのが実態と考えています。
対策費用とスティグマは表裏一体の関係であり、対策に「費用」をかければ、「安全性」の認識は高まり、スティグマは小さくなる。これまでの不動産市場で「掘削除去」が多くみられたのは、リスクが小さく、利用用途が広い不動産が望まれるからであり、だからこそ、対策に高い費用をかけても、より短期で確実に汚染を除去する方法が選択されてきたのだろうと思います。
今後、土壌汚染対策法の改正により、土壌汚染を残置した取引が多くなっていくのか・・・、この場合、「?」付きで示したもう一つの赤丸部分(図4)を不動産市場がどう捉えるのか、十分に市場の動向をウォッチしていく必要があると考えています。
まさに改正土壌汚染対策法が今年の4月に施行されましたが、今後の不動産市場の土壌汚染対応はどうなると予測しますか?
ん~、いきなり剛速球のストレートが来ましたね(笑)。
予測することはなかなか難しいですが、その点については、土壌汚染対策法の改正内容が見え始めた頃から、様々な企業の方々のご意見や対応の方向性などを伺っていますので、そうした内容と土壌汚染対策法改正のポイントを踏まえて、私なりの考えをお話ししたいと思います。(次回へつづく)
ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は、「土壌汚染対策法の改正が不動産市場に与える影響を考える(その1)」として、「掘削除去偏重は抑制されるのか?」についてお話しいただいた内容をお届けします。
