対談企画 サーキュラーエコノミーでハッピーになるのか
その4 所有権と資源循環
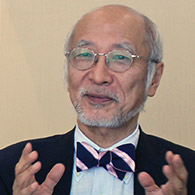
細田 衛士(ほそだ えいじ)様
東海大学学長補佐、政治経済学部経済学科・教授
慶應義塾大学名誉教授
中部大学理事、名誉教授
1993年より国税庁中央酒類審議会 新産業部会リサイクルワーキンググループ座長、1995年通商産業省産業構造審議会廃棄物小委員会委員、2000年運輸省FRP廃船の高度リサイクルシステム・プロジェクト推進委員会委員、2003年環境省政策評価委員会委員、2011年中央環境審議会委員、2011年林政審議会委員、2023年「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」事業における総会、ビジョン・ロードマップ検討ワーキンググループの委員などを歴任

粟生木 千佳(あおき ちか)様
公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 持続可能な消費と生産領域 主任研究員
2000年京都大学工学部卒業、2002年東京大学大学院工学系研究科修了(工学修士)。2007年政策研究大学院大学修了(国際開発学修士)。2023年9月立命館大学大学院理工学研究科後期博士課程修了(工学博士)2002年-2005年(株)野村総合研究所にて研究員/コンサルタントとして、環境ビジネス・環境政策関連調査/コンサルティングに従事。2007年6月IGES入所。循環経済・資源効率性向上に向けた政策研究や国際政策動向の調査・分析、循環経済・資源生産性指標の政策応用に関する調査研究を行っている。
■教育
細田
-

高度経済成長の時に雇用のシフトがうまくいった理由の1つに「教育力」があります。
工業高校では非常にいい教育指導が行われて、卒業後は地方のモノづくりに携わり、それなりにハッピーな生活をすることができて、非常に格差の少ない社会だった。というのが高度経済成長モデルでした。
それが、モノ作りが海外に出ていってしまうと、工業高校を卒業しても就職の場がなく、地方の産業が空洞化してきます。
そうすると、地域での雇用をどう作り上げるか、ということを考えないといけません。ポイントは2つあります。
1つ目は地域の循環をどうやって考えていくのか。これは地方創生の問題でもあります。
日本は地域循環を大事にしてきましたが、経済の安全保障や国防も含めて、地域がしっかりしていないと、水源を知らないうちに外国人に買われてしまったりすることだってあります。2つ目は、教育の質を変えていかないといけない。
経済成長を実現していた時、日本がなぜ強かったかというと、公立の初等教育の教育力の高さだと思います。教育力が高ければ、雇用調整能力も高いはずなんです。今、先生のなり手がいない、先生不足という大変な問題が生じています。教育力を上げて雇用調整能力を付けていくことは、時間がかかりますが、まだキャッチアップできると思っています。
粟生木
-
小学校の資料を見ると、私が想像するよりもSDGsも含む環境教育が良く行われていて驚くことがあります。
将来的には、この分野の専門的な高等教育に関心のある学生が増え、例えば、地域で出た食品廃棄物をエネルギーに変換して地域で使うなど、それぞれの地域で資源という意味で自立することが可能な社会経済システムの設計や実施を担えるような社会になることは非常に重要と思います。
■システムの転換
細田
-
小学生の授業で、自動車産業の教える時に、自動車の解体・リサイクルも一緒に教えるんです。動脈と静脈の両方を教える教育、作るだけでなく、どうやって使いまわしていくかという教育も必要だと思います。
我々の世代は、「ごみは捨てればいいじゃないか。焼却すればいいじゃないか。」という感覚が染みついています。確かに家庭ごみを清掃工場で燃やすのは、ごみ戦争を回避するために必要だったのですが、今は時代遅れになっていて、「捨てるということにはコストがかかる」、コストがかかるとしたらなるべく捨てないようにする、ということを認識しないといけませんね。
よく、再生資源化するコストが高いといわれるんですが、それは当たり前なんです。
なぜかって、「捨てる」ことを前提に経済システムが作られた社会の中では、「リサイクル」は高くなるんです。モノが循環利用される制度を作っておくと、捨てるコストが高くなり、リサイクルの費用が相対的に安くなります。社会システムが変わって、再生資源が集まりやすくなると、コストが下がりますし、大量に処理できると汎用技術が使えるようになりますので、コストは完全に逆転すると思いますよ。
粟生木
-

いろんな方と議論していて、現状の社会経済システムを想定して、資源循環を実現するための議論をしようとすると、コスト等の問題で難しいという結論になってしまいます。10年くらいのスパンで、動脈側と静脈側それぞれの技術やシステムの変化・発展がうまく合致する、すなわち、資源循環システムのコストが最適化されうる状況をイメージしながら、もしくはすり合わせるための方法を考えながら、実現に向けたプロセスを議論していくべきだろうなと思っています。
細田
-
再生資源が使われていくと、静脈産業の体力は増すのですが、そのためにはまず再生資源を集めないといけない。でも静脈産業に、まだそこまでの体力はない。
動静脈連携が推進されていますが、排出事業者側がきっちりと分別して排出して再生資源として利用するという発想にまだなっていないのですよね。
そうすると、捨てることへの制限、日本だと最終処分量の削減という制限もインセンティブになってくると思います。
■所有権と資源循環
細田
-
大きな枠組みでいうと、所有権をどう考えるか、ということだと思うんです。
長い資本主義の歴史は、私的所有が認められて物質的には豊かな社会ができました。でも、「捨てる」という行為が「作る」という行為にどうつながるか、経済学者の中でほとんど議論になってきませんでした。私的所有権を否定する共産主義はうまくいかないので、資本主義社会で考えると、捨てることをどこかで制約しておかないといけないと思うんです。
資源はいずれなくなりますので、今ある資源はみんなで使うようにしないといけない、という共有財のような性質もあり、いったん「保有」したならば、自分の知識と技術で十分に利益を取らないといけない。これは廃棄の責任を上流に持っていく、ということと関連します。
ご存じの通り、EUは衣料品や靴などの在庫の廃棄を禁止することにしました。
(参考)Ecodesign for Sustainable Products Regulation - European Commission
この「捨ててはいけない」というのは、所有権に対する強烈な宣言なんですよ。
所有権には、当然、処分権が入っていますので、処分権を制約するということは、所有権を制約しているということになります。捨ててはいけない、ということは使わなきゃいけないわけで、これは大胆なシフト、究極のサーキュラーエコノミーだと思います。こういう政策を大胆に打っていくところに、EUのすごさを感じています。

粟生木
-
捨てちゃいけないということもありますが、資源消費と経済発展のデカップリングの大前提として、「過剰に作らない」というのがありますよね。
例えば、ICTで需要予測をしたうえで生産したり、循環を想定した製品を作るなど、色々な方法があると思います。所有権や処分権を制限することも、過剰消費抑制につながるのでしょうか?
細田
-
捨てられなかったら、使わなければいけません。しかも、節約して利用しないといけなくなります。
上田
-
個人としては「要らなかったら捨てればいい」と気軽に買えなくなる、会社だと売れる見込みがなければ生産しにくくなる、ということでしょうか。
細田
-
我々の世代は「ごみなんて捨てればいいじゃん、燃やせばいいじゃん」という意識が染みついてしまっているのですが、将来へのロードマップとしては、「ただ捨てて燃やせばいい」というものではなく、捨てるということはコストがかかるんだということを、教育していくのも必要ですね。
日本人のいいところは「ものを大事にする」ところなのですが、もう1歩先のところで、「資源は循環して使う、使わないものは持たない(所有しない)」という認識を持たないといけません。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
