対談企画 サーキュラーエコノミーでハッピーになるのか
その2 グリーンな需要
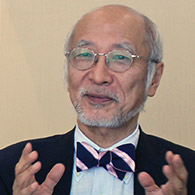
細田 衛士(ほそだ えいじ)様
東海大学副学長、政治経済学部経済学科・教授
慶應義塾大学名誉教授
中部大学理事、名誉教授
1993年より国税庁中央酒類審議会 新産業部会リサイクルワーキンググループ座長、1995年通商産業省産業構造審議会廃棄物小委員会委員、2000年運輸省FRP廃船の高度リサイクルシステム・プロジェクト推進委員会委員、2003年環境省政策評価委員会委員、2011年中央環境審議会委員、2011年林政審議会委員、2023年「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」事業における総会、ビジョン・ロードマップ検討ワーキンググループの委員などを歴任

粟生木 千佳(あおき ちか)様
公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 持続可能な消費と生産領域 主任研究員
2000年京都大学工学部卒業、2002年東京大学大学院工学系研究科修了(工学修士)。2007年政策研究大学院大学修了(国際開発学修士)。2023年9月立命館大学大学院理工学研究科後期博士課程修了(工学博士)2002年-2005年(株)野村総合研究所にて研究員/コンサルタントとして、環境ビジネス・環境政策関連調査/コンサルティングに従事。2007年6月IGES入所。循環経済・資源効率性向上に向けた政策研究や国際政策動向の調査・分析、循環経済・資源生産性指標の政策応用に関する調査研究を行っている。
■支払い意思
細田
-
供給があっても 需要がなければ経済成長は実現しませんので、ケインズ経済学的に考えれば需要の創出が非常に重要です。
サーキュラーエコノミー政策で、グリーンな社会、循環経済に変わるということは、経済構造が変わるということです。そうすると、生産供給能力も変わり、それに合わせたペースで需要が伸びてくれることが大事です。
需要がなければ、供給体制が整っても経済は成長しません。エレンマッカーサー財団やEUでは、「グリーンな供給が増えると、デマンド(需要)も増えてグリーンな社会に移行していく」と言うのですが、そんなに簡単な話ではありません。
なぜかというと、我々には所得制約がありますので、一方の需要が伸びると他の需要が縮む、ということがあり得るのです。つまりどのくらいグリーンな需要がネットで出てくるか、ということが極めて重要なんです。
上田
-
グリーンな需要というのはどういうものですか?
細田
-

先ほども話に出ました、環境負荷の小さい財やサービス、モノではなくコト、そして最近ではLINEやZOOMなどのアプリケーションにお金を使うのもそうですし、形がないものに対する支払い意思をどうやって創出していくかがポイントになります。
需要を作り出すということで、野球を例に話します。例えば日本のプロ野球とアメリカのMLBとを比べてみると、 MLBの収益は日本のNPBの収益の約6倍、16年連続の収益増です。だから選手に何十億円という年俸を出せるんです。
一方で日本のプロ野球の集金力は、それほど増えていません。
上田
-
どういうことですか?
細田
-
MBLは、お客さんの支払い意思を実現している、ということです。
プロ野球球団の収入源は、球場のチケット収入だけでなく、スポンサー収入や放映権などもあります。
いずれも、ファンが野球を楽しんだり、感動したり、力づけられたりすることの対価として、お金を払います。着るものや、 パソコンというような「モノ」ではなく、見て楽しむことや教養など、触れられない、インターンジブル(無形)な価値に対してお金を払うという、「モノ」に頼らない需要がグリーンな需要です。
粟生木
-

オランダの事例で、携帯電話をモジュール化してどんどんパーツを変えていくというサービスがあります。モジュールをカラフルなデザインにして、カラフルなデザインを入れ替える楽しみがある携帯電話もできうると思ったりしています。
他にもスマートフォンをメーカーが引き取って、自ら修理したり、リサイクルしてユーザーにポイントを返すことで、自社のユーザーを離さないような仕組みを構築し、そうすることで、付加的なサービス販売といったようなメリットにつながることもありうると思っています。
細田
-
スマートフォンメーカーが、スマートフォンを自ら回収して、精密に分解して、再生するという「リマニュファクチャリング」は、動脈と静脈が繋がっていて経済学的に、とても面白いんです。
粟生木さんがおっしゃったように囲い込み型のビジネスによってスマートフォンのユーザーを確保できるわけですよね。ただし、スマートフォンは、先進国で使用が終わっても、途上国では価値がある「グッズ(goods)」なものがあるのです。中古品として価値があると市場で流通するのでメーカーが回収したくても回収に回らず、メーカーによる囲い込みができないんです。
スマートフォンでも製品によっては価値のない「バッズ(bads)」になるものもあり、その場合は不用品として回収できてリサイクルに回せるのですが、いいもの、つまり価値のあるものを作ったがゆえに、グッズとして取引されてメーカーが回収したくても回収できないという、とても皮肉な現象が生じています。
そういうことはありますが、囲い込み方ビジネスは、需要を創出する1つのやり方で、競争がある限りビジネス戦略としてありだと思います。
■わくわく感
細田
-
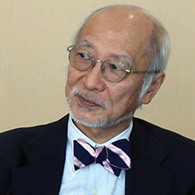
新しい資本主義、これは知識資本主義とも言うのですが、資源をあまり使わずに知的なものに支払い意思を実現させるというのは、スマートフォンのような形のあるモノだけでなく、見えないものに「わくわく感」をどう作っていくのか、ということです。
昔は労働者を雇って、同じ品質のものを安く大量に製造して、レッドオーシャンの中で激しい競争をしてきましたが、これからは、いかに付加価値性をつけるか、まさに知恵と知識そして情報が勝負の世界ですね。
例えば、もう着ない着物をジャケットに仕立て直して、外国人が買っていく時、それは着物の素材だけではない、付加価値がありますよね。そういう見えないもの、つまり付加価値をどうやって高めていくか、人にどうやってお金を払ってもらうか、というところは、シェアリングも含めて色々な手法がありますが、日本はまだ実現しきれていないと感じます。
粟生木
-
資源生産性を高めるためには、例えばタイヤや照明をどのぐらい使ったか、というデータをユーザーに提供するところに付加価値があるような製品やビジネスモデルへの転換も1つの方向性ですが、現状はいかに再生資源を使うか、という議論にとどまっていると感じます。
■再生資源の使用
粟生木
-

再生資源の利用に関しては、新しいビジネスモデルができるまでの間で最も取り組みやすい手段として非常に重要だと思いますし、再生資源の利用を通じて天然資源の使用を抑制することは、脱炭素社会を実現していく中で重要なポイントになってきます。
技術革新で個別の技術を上げていくことも必要ですが、静脈資源をどう集めて、どう確保するか、回収や収集の広域化・効率化など、社会システム全体を変えないと、コストが下がっていかないという課題があるのではと考えています。
細田
-
メーカーの方と話をしていると、再生資源を使いなさいといわれても、再生資源は安定調達できるんですか?安定調達できないものは使えませんよ、と言われるんです。鶏が先か卵が先か、ですが、資源性を持った静脈資源を確保して回収しないと再生資源は生産できませんし、再生資源を使わないと再生資源は生産されません。
現実的な問題としてシステム設計に組み込む必要がありますが、例えば、自動車に再生資源を使うインセンティブシステムが動き始めているので、少しずつ進んでいくと思います。
ご存じの通り、ペットボトルは、再生ペットボトルの方がバージンのペットボトルより、価格が高くなっています。なぜかというと、SDGsの流れもありますし、全国清涼飲料連合会が、2030年までに50%はボトルtoボトルにすると宣言しました。100%リサイクルペットボトルの導入を目指しているメーカーもあります。
法律はありませんが、そういった制約や自主的な取り組みによって再生資源を使う方向が見えてきて、再生資源が取り合いになってきているのです。

粟生木
-
EU政策を見ていると、再生資源を使うという大枠を作ることによって将来的に社会システムを変革していくことを想定して動いているように見えます。
先ほど先生が、「需要」を作り出すことが大切とおっしゃった時に、どんどん製品を新しく作るのか?と、少し混乱したのですが、「枠」を作ることによって再生資源への需要を生み出して社会がシフトしていく、ということになりえるんですね。
以前、自治体のサーキュラーエコノミー政策立案のお手伝いをした時に、well-beingがわかりにくいという指摘をいただいて、その通りなんですが、この場合どういうことなのかを考えたことがあります。その時、なんらかの産業と雇用、そして一定の所得が確保されるということかなと整理したんです。
製造拠点が海外に移転して、地方に仕事がないという状況になっていますので、資源が循環することによって産業が活性化されて、日本の産業が空洞化しないという状況を作れるのか、というところを考えてみたいと思っています。
細田
-
EUはまさに、それを考えているんですよね。
理想的なことばっかり言っている気がしますが、目指すところはそこなんだろうと思います。
粟生木
-
そうなんです。
彼らは、脱炭素社会にシフトしていかないといけない中で、既存産業の雇用を吸収するための策として、サーキュラーエコノミーを考えているんだろうと推察しています。おそらく日本も、脱炭素がきっかけになるのかはわかりませんが、サーキュラーエコノミーを使ってうまくシフトしてくことができるような制度設計をしないといけないのだろうと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は、「社会における雇用の流動性」についてお話しいただきます。
